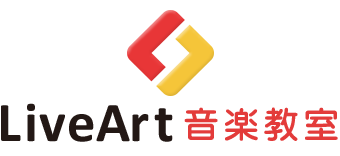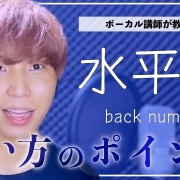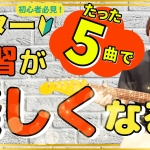гАРжЭ±дЇђгБЃгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гАС иЗ™еЃЕзЈізњТгБІйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБМеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛеИЖгБЛгВЙгБ™гБДжЦєгБЄгБЃдЄКйБФгБЃгВ≥гГДпЉБ
гАРгГЬгГЉгВЂгГЂеИЭењГиАЕењЕи¶ЛгАС
иЗ™еЃЕзЈізњТгБІйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБМеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛгВТ
祯еЃЯгБЂгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛгБКгБЩгБЩгВБжЦєж≥ХгБ®
дЄКйБФгБЃгВ≥гГД
зЫЃжђ°
- гБѓгБШгВБгБЂпЉЪиЗ™еЃЕзЈізњТгБІгВИгБПгБВгВЛйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБЃжВ©гБњ
- гБ™гБЬйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгВЛгБЃгБЛпЉЯеОЯеЫ†гВТеЊєеЇХиІ£и™ђ
- иЗ™еИЖгБЃж≠МгВТж≠£гБЧгБПгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛ5гБ§гБЃжЦєж≥Х
- йЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гВТйНЫгБИгВЛгБКгБЩгБЩгВБзД°жЦЩгВҐгГЧгГ™гБ®ж©ЯжЭР
- иЗ™еЃЕзЈізњТгБІдљњгБИгВЛйЯ≥з®ЛпЉЖгГ™гВЇгГ†еЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
- еИЭењГиАЕгБМгВДгВКгБМгБ°гБ™NGзЈізњТж≥Х
- иЗ™еЃЕгГЬгВ§гГИгГђзЈізњТгВТжЬАе§ІеМЦгБЩгВЛзњТжЕ£гБ•гБПгВК
- гВИгБПгБВгВЛи≥™еХПгБ®гГЧгГ≠гБЃеЫЮз≠Ф
- гБЊгБ®гВБпЉЪйЯ≥з®ЛгБ®гГ™гВЇгГ†гБѓгАМиА≥гАНгБ®гАМзњТжЕ£гАНгБІе§ЙгВПгВЛ

гБѓгБШгВБгБЂ
иЗ™еЃЕзЈізњТгБІгВИгБПгБВгВЛйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБЃжВ©гБњ
гГЬгГЉгВЂгГЂгБЃзЈізњТгБѓгАБењЕгБЪгБЧгВВгВєгВњгВЄгВ™гВДгГђгГГгВєгГ≥гГЂгГЉгГ†гБ†гБСгБІи°МгБЖгВВгБЃгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ
е§ЪгБПгБЃжЦєгБѓгАБдїХдЇЛгВДе≠¶ж†°гБЃеРИйЦУгАБиЗ™еЃЕгБІгБЃйЩРгВЙгВМгБЯжЩВйЦУгВТдљњгБ£гБ¶ж≠МгБЃзЈізњТгВТгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЧгБЛгБЧгАБгБЭгБЃиЗ™еЃЕзЈізњТгБІгАМйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБЛеИЖгБЛгВЙгБ™гБДгАНгБ®гБДгБЖжВ©гБњгВТжК±гБИгВЛжЦєгБѓйЭЮеЄЄгБЂе§ЪгБДгБІгБЩгАВ
гБУгВМгБѓеИЭењГиАЕгБЂйЩРгВЙгБЪгАБдЄ≠зіЪиАЕгАБе†іеРИгБЂгВИгБ£гБ¶гБѓгГЧгГ≠ењЧеРСгБЃжЦєгБІгВВиµЈгБУгВКеЊЧгВЛи™≤й°МгБІгБЩгАВ
зІБгБМйБЛеЦґгБЩгВЛжЭ±дЇђгБЃLiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІгВВгАБгБУгБЃи≥™еХПгБѓеєійЦУгВТйАЪгБЧгБ¶дљХеЇ¶гВВгБДгБЯгБ†гБНгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂе§ЪгБДжВ©гБњгБЃе£∞
вЖУ
- дЉіе•ПгБЂеРИгВПгБЫгБ¶ж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛгБ§гВВгВКгБ™гБЃгБЂгАБйМ≤йЯ≥гБЩгВЛгБ®гВЇгГђгБ¶гБДгВЛвА¶
- йЯ≥гБѓеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®жАЭгБЖгБСгБ©гАБгБ™гВУгБ®гБ™гБПйБХеТМжДЯгБМгБВгВЛвА¶
- гВЂгГ©гВ™гВ±жО°зВєгБЃзВєжХ∞гБѓжВ™гБПгБ™гБДгБЃгБЂгАБгГЧгГ≠гБ£гБљгБПиБЮгБУгБИгБ™гБДвА¶
- дЉіе•ПгБ™гБЧгБІж≠МгБЖгБ®жЬАеИЭгБЃйЯ≥гВТе§ЦгБЧгБ¶гБЧгБЊгБЖвА¶
- гГЖгГ≥гГЭгБМеЃЙеЃЪгБЫгБЪгАБж≠МгБДеЗЇгБЧгБМйБЕгВМгБЯгВКиµ∞гБ£гБЯгВКгБЩгВЛвА¶
гБ™гБЬгАМеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛеИЖгБЛгВЙгБ™гБДгАНзКґжЕЛгБЂгБ™гВЛгБЃгБЛпЉЯ
еОЯеЫ†гБЃе§ЪгБПгБѓгАБгАМеЃҐи¶≥зЪДгБ™иА≥гАНгБІиЗ™еИЖгБЃж≠МгВТиБігБСгБ¶гБДгБ™гБДгБУгБ®гАВ
ж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛжЬАдЄ≠гБѓгАБиЗ™еИЖгБЃе£∞гВТй™®дЉЭе∞ОгВДз©Їж∞ЧжМѓеЛХгБІиБігБДгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБеЃЯйЪЫгБЂе§ЦгБЂйЯњгБДгБ¶гБДгВЛе£∞гБ®гБѓзХ∞гБ™гВЛйЯ≥гВТи™Ни≠ШгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБ§гБЊгВКгАМиЗ™еИЖгБІгБѓеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБ§гВВгВКгАНгБІгВВгАБе§ЦгБЛгВЙиБігБПгБ®гВЇгГђгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖзПЊи±°гБМиµЈгБУгВКгБЊгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂгАБиЗ™еЃЕзЈізњТзЙєжЬЙгБЃзТ∞еҐГи¶БеЫ†гВВеК†гВПгВКгБЊгБЩгАВ
йЭЩгБЛгБ™йГ®е±ЛгБІе∞ПгБХгБ™дЉіе•ПйЯ≥гБЂеРИгВПгБЫгБ¶ж≠МгБЖгБ®гАБдЉіе•ПгБМгБЧгБ£гБЛгВКиА≥гБЂе±КгБЛгБЪгАБгГ™гВЇгГ†гВДйЯ≥з®ЛгБМзЛђгВКж≠©гБНгБЧгВДгБЩгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгВ§гГ§гГЫгГ≥гВДгВєгГФгГЉгВЂгГЉгБЃи≥™гАБйЯ≥йЗПи®≠еЃЪгБ™гБ©гВВеЊЃе¶ЩгБ™гВЇгГђгБЃеОЯеЫ†гБІгБЧгВЗгБЖгАВ
гВИгБПгБВгВЛ3гБ§гБЃгГСгВњгГЉгГ≥
LiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІеЃЯйЪЫгБЂе§ЪгБДгВ±гГЉгВєгВТжХізРЖгБЩгВЛгБ®гАБжђ°гБЃ3гГСгВњгГЉгГ≥гБЂеИЖй°ЮгБІгБНгБЊгБЩгАВ
- йЯ≥з®ЛгБМеЃЙеЃЪгБЧгБ™гБДгВњгВ§гГЧ
йЂШйЯ≥гБЂгБ™гВЛгБ®еКЫгВУгБІгВЈгГ£гГЉгГЧпЉИйЂШгВБпЉЙгБЂе§ЦгВМгВЛгАБдљОйЯ≥гБЂгБ™гВЛгБ®гГХгГ©гГГгГИпЉИдљОгВБпЉЙгБЂе§ЦгВМгВЛгАВ
йЯ≥жДЯгБѓжВ™гБПгБ™гБДгБМгАБе£∞гБЃгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБМеЃЙеЃЪгБЧгБ¶гБДгБ™гБДгВ±гГЉгВєгБІгБЩгАВ - гГ™гВЇгГ†гБМиµ∞гВЛ/йБЕгВМгВЛгВњгВ§гГЧ
зЈКеЉµгВДгГЖгГ≥гВЈгГІгГ≥гБЃйЂШгБЊгВКгБІгГЖгГ≥гГЭгБМйАЯгБПгБ™гВЛпЉИиµ∞гВЛпЉЙгАБгБЊгБЯгБѓж≠Ми©ЮгВТжДПи≠ШгБЧгБЩгБОгБ¶йБЕгВМгВЛгАВ
зЙєгБЂж≠МгБДеЗЇгБЧгБЃ1жЛНзЫЃгБІгВЇгГђгВЛдЇЇгБМе§ЪгБДгБІгБЩгАВ - иЗ™еЈ±еИ§жЦ≠гБМгБІгБНгБ™гБДгВњгВ§гГЧ
ж≠МгБДгБ™гБМгВЙгАМгБУгВМгБІеРИгБ£гБ¶гВЛпЉЯгАНгБ®дЄНеЃЙгБЂгБ™гВКгАБжЬАеЊМгБЊгБІйЫЖдЄ≠гБІгБНгБ™гБДгАВ
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБѓе§ІгБНгБПгВЇгГђгБ¶гБДгБ™гБДгБМгАБиЗ™еЈ±и©ХдЊ°гБЃеЯЇжЇЦгБМгБ™гБДгБЯгВБиЗ™дњ°гВТжМБгБ¶гБ™гБДгВ±гГЉгВєгБІгБЩгАВ
гБУгБЃи®ШдЇЛгБІеЊЧгВЙгВМгВЛгБУгБ®
гБУгБЃи®ШдЇЛгБІгБѓгАБгБУгБЖгБЧгБЯгАМиЗ™еЃЕзЈізњТгБІгБЃйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†дЄНеЃЙгАНгВТиІ£жґИгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгАБжђ°гБЃеЖЕеЃєгВТзґ≤зЊЕзЪДгБЂиІ£и™ђгБЧгБЊгБЩгАВ
- йЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгВЛеОЯеЫ†гБ®гБЭгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†
- иЗ™еЃЕгБІгБІгБНгВЛж≠£зҐЇгБ™иЗ™еЈ±гГБгВІгГГгВѓжЦєж≥Х
- гВєгГЮгГЫгВДзД°жЦЩгВҐгГЧгГ™гВТдљњгБ£гБЯеЃЯиЈµзЪДгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
- йЦУйБХгБ£гБЯзЈізњТж≥ХгБ®гБЭгБЃжФєеЦДз≠Ц
- жѓОжЧ•гБЃзЈізњТгВТеКєжЮЬзЪДгБЂгБЩгВЛзњТжЕ£гБ•гБПгВК
зЙєеИ•гБ™йЯ≥ж•љзЯ•и≠ШгБМгБ™гБПгБ¶гВВзРЖиІ£гБІгБНгВЛгВИгБЖгАБе∞ВйЦАзФ®и™ЮгБѓгБІгБНгВЛгБ†гБСеЩЫгБњз†ХгБДгБ¶и™ђжШОгБЧгБЊгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂгАБLiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБЃгГђгГГгВєгГ≥зПЊе†ігБІеЃЯйЪЫгБЂеКєжЮЬгБМгБВгБ£гБЯжЦєж≥ХгВВдЇ§гБИгБ¶гБКдЉЭгБИгБЧгБЊгБЩгБЃгБІгАБжШОжЧ•гБЛгВЙгБЃиЗ™еЃЕгГЬгВ§гГИгГђзЈізњТгБЂгБЩгБРжіїгБЛгБЫгБЊгБЩгАВ
иЗ™еЃЕзЈізњТгВТгАМиЗ™еЈ±жµБгБЃгБЊгБЊгАНгБЂгБЧгБ™гБДгБЯгВБгБЂ
ж≠МгБЃдЄКйБФгБІдЄАзХ™жАЦгБДгБЃгБѓгАБйЦУйБХгБ£гБЯгБЊгБЊзЈізњТгВТзґЪгБСгБ¶гБЧгБЊгБЖгБУгБ®гАВ
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМеЊЃе¶ЩгБЂгВЇгГђгБЯзКґжЕЛгВТжѓОжЧ•зє∞гВКињФгБЩгБ®гАБгБЭгБЃгВЇгГђгБМгАМиЗ™еИЖгБЃж≠£иІ£гАНгБЂгБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩгАВ
гБУгБЖгБ™гВЛгБ®дњЃж≠£гБЂжЩВйЦУгБМгБЛгБЛгВКгАБж≠МгБЃдЄКйБФгБЃгВєгГФгГЉгГЙгБМе§ІеєЕгБЂиРљгБ°гБЊгБЩгАВ
гБЭгБЃгБЯгВБгАБиЗ™еЃЕзЈізњТгБІгБѓгАМж≠£гБЧгБДиА≥гБЃдљњгБДжЦєгАНгБ®гАМеЃҐи¶≥зЪДгБ™гГБгВІгГГгВѓгАНгБМдЄНеПѓжђ†гБІгБЩгАВ
гБУгВМгБХгБИиЇЂгБЂгБ§гБСгВМгБ∞гАБзЛђе≠¶гБІгВВй©ЪгБПгБїгБ©еЃЙеЃЪгБЧгБЯж≠МгБМж≠МгБИгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жђ°зЂ†гБЛгВЙгБѓгАБгБЊгБЪгАМгБ™гБЬйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгВЛгБЃгБЛпЉЯгАНгБ®гБДгБЖж†єжЬђеОЯеЫ†гВТи©≥гБЧгБПи¶ЛгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгВЗгБЖпЉБ

зђђпЉТзЂ†
гБ™гБЬйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгВЛгБЃгБЛпЉЯ
еОЯеЫ†гВТеЊєеЇХиІ£и™ђ
иЗ™еЃЕгБІж≠МгБЃзЈізњТгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гАБгАМгБВгВМгАБгБ™гВУгБ†гБЛдЉіе•ПгБ®еРИгБ£гБ¶гБДгБ™гБДвА¶гАНгБ®жДЯгБШгВЛзЮђйЦУгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃеОЯеЫ†гБѓеНШзіФгБІгБѓгБ™гБПгАБгБДгБПгБ§гБЛгБЃи¶Бзі†гБМзµ°гБњеРИгБ£гБ¶иµЈгБНгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБУгБУгБІгБѓгАБйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгВЛдЄїгБ™еОЯеЫ†гВТгАМиЇЂдљУзЪДи¶БеЫ†гАНгАМиБіи¶ЪзЪДи¶БеЫ†гАНгАМзТ∞еҐГзЪДи¶БеЫ†гАНгБЃ3гБ§гБЂеИЖгБСгБ¶иІ£и™ђгБЧгБЊгБЩгАВ
1. иЇЂдљУзЪДи¶БеЫ†
иЇЂдљУзЪДи¶БеЫ†гБ®гБѓгАБе£∞гВТеЗЇгБЩгБЯгВБгБЃз≠ЛиВЙгВДеСЉеРЄгБЃдљњгБДжЦєгБМеОЯеЫ†гБІгВЇгГђгБ¶гБЧгБЊгБЖгВ±гГЉгВєгБІгБЩгАВ
- зЩЇе£∞з≠ЛгБЃгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂдЄНиґ≥
йЂШйЯ≥гБЂгБ™гВЛгБ®еЦЙгБМзЈ†гБЊгВКгАБе£∞гБМењЕи¶Бдї•дЄКгБЂйЂШгБПгБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБЖпЉИгВЈгГ£гГЉгГЧгБЩгВЛпЉЙгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
йАЖгБЂдљОйЯ≥гБІгБѓе£∞еЄѓгБЃйЦЙгБШжЦєгБМзЈ©гБњгАБйЯ≥гБМдЄЛгБМгБ£гБ¶гБЧгБЊгБЖпЉИгГХгГ©гГГгГИгБЩгВЛпЉЙгБУгБ®гВВгАВ - еСЉеРЄгБЃдЄНеЃЙеЃЪгБХ
жБѓгБЃжФѓгБИгБМеЉ±гБДгБ®е£∞гБМжПЇгВМгАБйЯ≥з®ЛгБМдЄНеЃЙеЃЪгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂйХЈгБДгГХгГђгГЉгВЇгБЃжЬАеЊМгБѓжБѓгБМиґ≥гВКгБЪгБЂйЯ≥гБМдЄЛгБМгВКгБМгБ°гБІгБЩгАВ - дљУгБЃзЈКеЉµ
еІњеЛҐгБМжВ™гБДгАБиВ©гВДй¶ЦгБМеКЫгВУгБІгБДгВЛгБ®е£∞гБЃйЯњгБНгБМз°ђгБПгБ™гВКгАБе£∞гБЃгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБМеКєгБЛгБ™гБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
зµРжЮЬгБ®гБЧгБ¶гАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМеЊЃе¶ЩгБЂгВЇгГђгБЊгБЩгАВ
2. иБіи¶ЪзЪДи¶БеЫ†
ж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛжЬАдЄ≠гБЂиБігБУгБИгБ¶гБПгВЛиЗ™еИЖгБЃе£∞гБѓгАБеЃЯгБѓгАМе§ЦгБЃйЯ≥гАНгБ®еРМгБШгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ
гБУгВМгБѓй™®дЉЭе∞ОгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛзПЊи±°гБМйЦҐдњВгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
й™®дЉЭе∞ОгБ®гБѓгАБе£∞еЄѓгБЛгВЙй†≠иУЛй™®гВТйАЪгБШгБ¶зЫіжО•еЖЕиА≥гБЂе±КгБПйЯ≥гБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ
гБУгБЃгБЯгВБгАБеЃЯйЪЫгБЂз©Їж∞ЧдЄ≠гВТдЉЭгВПгБ£гБ¶гГЮгВ§гВѓгВДдїЦдЇЇгБЃиА≥гБЂе±КгБПйЯ≥гВИгВКгВВгАБдљОгБПгГїжЯФгВЙгБЛгБПиБігБУгБИгВЛеВЊеРСгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБ§гБЊгВКгАБиЗ™еИЖгБЃиА≥гБІиБігБДгБ¶гБДгВЛйЯ≥гБѓгАМжЬђзЙ©гАНгБ®гВЇгГђгБ¶гБДгВЛеПѓиГљжАІгБМйЂШгБДгБЃгБІгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгГ™гВЇгГ†жДЯгБЂгВВиБіи¶ЪгБѓе§ІгБНгБПељ±йЯњгБЧгБЊгБЩгАВ
дЉіе•ПгВТиБігБНеПЦгВКгБЂгБПгБДзТ∞еҐГгБІгБѓгАБж≠£гБЧгБДжЛНжДЯгВТжДЯгБШгВЙгВМгБЪгАБиµ∞гБ£гБЯгВКйБЕгВМгБЯгВКгБЧгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂгВ§гГ§гГЫгГ≥гБЃзЙЗиА≥гБ†гБСгБІзЈізњТгБЩгВЛгБ®гАБгВєгГЖгГђгВ™жДЯгБМ姱гВПгВМгАБжЛНгБЃдљНзљЃгВТгБ§гБЛгБњгБЂгБПгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
3. зТ∞еҐГзЪДи¶БеЫ†
иЗ™еЃЕзЈізњТгБ™гВЙгБІгБѓгБЃгАМзТ∞еҐГгБЃиРљгБ®гБЧз©ігАНгВВи¶ЛйАГгБЫгБЊгБЫгВУгАВ
- дЉіе•ПйЯ≥йЗПгБМе∞ПгБХгБД
гВєгГФгГЉгВЂгГЉгВДгВ§гГ§гГЫгГ≥гБЃйЯ≥йЗПгБМе∞ПгБХгБДгБ®гАБиЗ™еИЖгБЃе£∞гБ∞гБЛгВКгБМиА≥гБЂеЕ•гВКгАБдЉіе•ПгБ®гБЃгВЇгГђгВТжДЯзЯ•гБЧгБЂгБПгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ - еПНйЯњгБМе∞СгБ™гБДйГ®е±Л
еРЄйЯ≥жАІгБЃйЂШгБДйГ®е±ЛпЉИгВЂгГЉгГЪгГГгГИгАБгВЂгГЉгГЖгГ≥гАБеЃґеЕЈгБМе§ЪгБДйГ®е±ЛпЉЙгБѓгАБе£∞гБЃйЯњгБНгБМиА≥гБЂе±КгБНгБЂгБПгБПгАБйЯ≥з®ЛгБМдљОгБПжДЯгБШгВДгБЩгБДгБІгБЩгАВ - йМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїгБЃзњТжЕ£гБМгБ™гБД
гГ™гВҐгГЂгВњгВ§гГ†гБІж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®гБНгБѓгВЇгГђгБЂж∞ЧгБ•гБСгБ™гБПгБ¶гВВгАБйМ≤йЯ≥гВТиБігБПгБ®дЄАзЫЃзЮ≠зДґгБІгБЩгАВйМ≤йЯ≥гБЧгБ™гБДзњТжЕ£гБѓгАБгВЇгГђгБЃгАМж∞ЧгБ•гБНгАНгВТйБЕгВЙгБЫгБЊгБЩгАВ
4. ењГзРЖзЪДи¶БеЫ†
жДПе§ЦгБ®и¶ЛиРљгБ®гБЧгБМгБ°гБ™гБЃгБМгАБењГзРЖзЪДгБ™и¶БеЫ†гБІгБЩгАВ
- дЄНеЃЙгВДзЈКеЉµ
гАМйЦУйБХгБИгБЯгВЙгБ©гБЖгБЧгВИгБЖгАНгБ®иАГгБИгБ™гБМгВЙж≠МгБЖгБ®гАБйЫЖдЄ≠еКЫгБМеИЖжХ£гБЧгАБжЛНгБЃгВЂгВ¶гГ≥гГИгВТи¶Л姱гБДгВДгБЩгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ - иЗ™еЈ±и©ХдЊ°гБЃеЯЇжЇЦгБМгБ™гБД
гАМгБУгБЃйЯ≥гБМж≠£гБЧгБДгАНгБ®гБДгБЖжШО祯гБ™еЯЇжЇЦгВТжМБгБЯгБ™гБДгБЊгБЊзЈізњТгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гАБжДЯи¶ЪгБЂй†ЉгВКгБЩгБОгБ¶гВЇгГђгБМзФЯгБШгБЊгБЩгАВ - иА≥гБМвАЬжЕ£гВМгБ¶гБДгБ™гБДвАЭ
йЯ≥жДЯгВДгГ™гВЇгГ†жДЯгБѓгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞гБІиВ≤гБ¶гВЛгВВгБЃгБІгБЩгАВ
гБЊгБ†иА≥гБМиВ≤гБ£гБ¶гБДгБ™гБДжЃµйЪОгБІгБѓгАБж≠£зҐЇгБ™йЯ≥гВДжЛНгВТеИ§жЦ≠гБЩгВЛгБУгБ®иЗ™дљУгБМйЫ£гБЧгБДгБЃгБІгБЩгАВ
гВЇгГђгБЃеОЯеЫ†гБѓи§ЗеРИзЪДгБЂзПЊгВМгВЛ
е§ЪгБПгБЃе†іеРИгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгБѓ1гБ§гБЃеОЯеЫ†гБ†гБСгБІиµЈгБНгВЛгВПгБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ
дЊЛгБИгБ∞гАМйЂШйЯ≥гБМе§ЦгВМгВЛгАНгВ±гГЉгВєгБІгБѓгАБзЩЇе£∞з≠ЛгБЃзЈКеЉµпЉИиЇЂдљУзЪДи¶БеЫ†пЉЙпЉЛдЉіе•ПгБЃиБігБНеПЦгВКдЄНиґ≥пЉИиБіи¶ЪзЪДи¶БеЫ†пЉЙгБМеРМжЩВгБЂдљЬзФ®гБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
еОЯеЫ†гБМи§ЗеРИгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гАБиЗ™еИЖгБІгБѓгАМдљХгБМжВ™гБДгБЃгБЛгАНеИ§жЦ≠гБЧгБ•гВЙгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гБ†гБЛгВЙгБУгБЭгАБжђ°зЂ†гБІиІ£и™ђгБЩгВЛгВИгБЖгБЂгАБеЃҐи¶≥зЪДгБ™гГБгВІгГГгВѓжЦєж≥ХгВТжМБгБ§гБУгБ®гБМйЗНи¶БгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жђ°гБЃзђђ3зЂ†гБІгБѓгАБиЗ™еИЖгБЃж≠МгВТж≠£гБЧгБПи©ХдЊ°гБЧгАБйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгВТиЗ™еЃЕгБІз∞°еНШгБЂзЩЇи¶ЛгБІгБНгВЛжЦєж≥ХгВТ5гБ§зієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ

жЭ±дЇђгБЃLiveArtгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гБѓгБУгБ°гВЙ
зђђпЉУзЂ†
иЗ™еИЖгБЃж≠МгВТж≠£гБЧгБПгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛ
5гБ§гБЃжЦєж≥Х
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гВТж≠£зҐЇгБЂгБЩгВЛгБЯгВБгБЃзђђдЄАж≠©гБѓгАБгАМиЗ™еИЖгБЃж≠МгВТеЃҐи¶≥зЪДгБЂиБігБПгАНгБУгБ®гАВ
гБУгВМгБМгБІгБНгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВЛгБ®гАБеОЯеЫ†гБЃзЙєеЃЪгВДжФєеЦДгБМй£ЫиЇНзЪДгБЂжЧ©гБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гБУгБУгБІгБѓгАБиЗ™еЃЕзЈізњТгБІгВВз∞°еНШгБЂгБІгБНгВЛ5гБ§гБЃгГЬгВ§гГИгГђгГБгВІгГГгВѓжЦєж≥ХгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ
1. гВєгГЮгГЫгБІйМ≤йЯ≥гБЧгБ¶иБігБНињФгБЩ
жЬАгВВгВЈгГ≥гГЧгГЂгБІеКєжЮЬзЪДгБ™жЦєж≥ХгБМйМ≤йЯ≥гБІгБЩгАВ
гВєгГЮгГЫгБЃгГЬгВ§гВєгГ°гГҐгВДгГђгВ≥гГЉгГАгГЉгВҐгГЧгГ™гВТдљњгБ£гБ¶гАБиЗ™еИЖгБЃж≠Ме£∞гВТйМ≤йЯ≥гБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
гГЭгВ§гГ≥гГИгБѓдї•дЄЛгБЃ3гБ§гБІгБЩгАВ
- дЉіе•ПгБ®дЄАзЈТгБЂйМ≤гВЛ вАФ гВҐгВЂгГЪгГ©гБІгБѓгБ™гБПгАБењЕгБЪдЉіе•ПгВТжµБгБЧгБ™гБМгВЙйМ≤йЯ≥гБЩгВЛгАВ
- гГѓгГ≥гВ≥гГЉгГ©гВєгБФгБ®гБЂеМЇеИЗгВЛ вАФ йХЈгБЩгБОгВЛйМ≤йЯ≥гБѓгГБгВІгГГгВѓгБМе§Іе§ЙгАВзЯ≠гБПеМЇеИЗгВЛгБ®жФєеЦДзВєгБМжШО祯гБЂгБ™гВЛгАВ
- йЯ≥йЗПгГРгГ©гГ≥гВєгВТ祯и™НгБЩгВЛ вАФ е£∞гБМдЉіе•ПгВИгВКе§ІгБНгБЩгБОгБ¶гВВе∞ПгБХгБЩгБОгБ¶гВВгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгБМеИ§жЦ≠гБЧгБ•гВЙгБПгБ™гВЛгАВ
йМ≤йЯ≥гВТиБігБПгБ®гАБж≠МгБ£гБ¶гБДгВЛжЬАдЄ≠гБЂгБѓж∞ЧгБ•гБЛгБ™гБЛгБ£гБЯзі∞гБЛгБДгВЇгГђгБМгВИгБПеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂгАМи™Юе∞ЊгБЃйЯ≥з®ЛгБМдЄЛгБМгБ£гБ¶гБДгВЛгАНгАМж≠МгБДеЗЇгБЧгБЃгВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гБМжЧ©гБДгАНгБ™гБ©гАБиА≥гБІиБігБДгБ¶еИЭгВБгБ¶еИЖгБЛгВЛжФєеЦДзВєгБМе§ЪгБДгБІгБЩгАВ
2. йМ≤зФїгБЧгБ¶еП£гБЃеЛХгБНгГїеІњеЛҐгВВгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛ
йМ≤йЯ≥гБЂеК†гБИгБ¶гАБеЛХзФїгБІиЗ™еИЖгБЃж≠МгВТжТЃгВЛгБ®гАБеІњеЛҐгВДеП£гБЃеЛХгБНгБЊгБІзҐЇи™НгБІгБНгБЊгБЩгАВ
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгБѓгАБиЇЂдљУгБЃдљњгБДжЦєгБ®гВВеѓЖжО•гБЂйЦҐдњВгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЯгБ®гБИгБ∞вА¶
- йЂШйЯ≥гБІй°ОгБМдЄКгБМгБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгАБеЦЙгБМзЈ†гБЊгБ£гБ¶гБДгВЛ
- гГЖгГ≥гГЭгБМиµ∞гВЛгБ®гБНгБѓиЇЂдљУеЕ®дљУгБМеЙНгБЃгВБгВКгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛ
- йБЕгВМгВЛгБ®гБНгБѓи¶ЦзЈЪгБМдЄЛгБМгВКгАБеСЉеРЄгБМжµЕгБПгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛ
гБУгБЖгБЧгБЯгВѓгВїгБѓйЯ≥е£∞гБ†гБСгБІгБѓеИЖгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ
еЛХзФїгБІзҐЇи™НгБЧгАБжДПи≠ШзЪДгБЂдњЃж≠£гБЧгБ¶гБДгБПгБУгБ®гБМйЗНи¶БгБІгБЩгАВ
3. гГФгГГгГБ祯и™НгВҐгГЧгГ™гВТдљњгБЖ
ињСеєігБѓгВєгГЮгГЫгВҐгГЧгГ™гБІгГ™гВҐгГЂгВњгВ§гГ†гБЃйЯ≥з®Ли°®з§ЇгБМеПѓиГљгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
дї£и°®зЪДгБ™гВВгБЃгБЂгАМVocal Pitch MonitorгАНгАМSingScopeгАНгБ™гБ©гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБУгВМгВЙгБЃгВҐгГЧгГ™гВТдљњгБЖгБ®гАБиЗ™еИЖгБЃж≠МгБ£гБЯйЯ≥гБМгВ∞гГ©гГХгБ®гБЧгБ¶и°®з§ЇгБХгВМгАБдЉіе•ПгБЃж≠£гБЧгБДйЯ≥гБ®гБЃгВЇгГђгВТи¶Ци¶ЪзЪДгБЂзҐЇи™НгБІгБНгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂељєзЂЛгБ§гБЃгБѓжђ°гБЃгВИгБЖгБ™е†ійЭҐ
вЖУ
- гАМгБУгБЃйЂШйЯ≥гАБеНКйЯ≥йЂШгБПгБ™гБ£гБ¶гБ™гБДгБЛгБ™пЉЯгАНгБ®гБДгБЖеЊЃе¶ЩгБ™гВЇгГђгБЃзҐЇи™Н
- йЯ≥з®ЛгБМеЃЙеЃЪгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгАБгБЊгБ£гБЩгБРзЈЪгБМеЉХгБСгБ¶гБДгВЛгБЛгВТгГБгВІгГГгВѓ
- гГХгГђгГЉгВЇгБФгБ®гБЃйЯ≥гБЃеЗЇзЩЇзВєгБМж≠£гБЧгБДгБЛгБ©гБЖгБЛгБЃзҐЇи™Н
гБЯгБ†гБЧгАБгВҐгГЧгГ™гБЃжХ∞еА§гБ∞гБЛгВКж∞ЧгБЂгБЩгВЛгБ®гАБжДЯи¶ЪгБІж≠МгБЖеКЫгБМеЉ±гБЊгВЛжБРгВМгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гАМжДЯи¶ЪгБЃзҐЇи™НгГДгГЉгГЂгАНгБ®гБЧгБ¶дљњгБЖгБЃгБМзРЖжГ≥гБІгБЧгВЗгБЖгАВ
4. гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІжЛНгВТеПѓи¶ЦеМЦгБЩгВЛ
гГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгБѓиА≥гБ†гБСгБІеИ§жЦ≠гБЩгВЛгБЃгБМйЫ£гБЧгБДе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЭгБУгБІељєзЂЛгБ§гБЃгБМгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІгБЩгАВ
гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гВТдљњгБ£гБЯгГБгВІгГГгВѓжЦєж≥ХгБѓдї•дЄЛгБЃйАЪгВКгБІгБЩгАВ
- жЫ≤гБЃгГЖгГ≥гГЭгВТи™њгБєгАБгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБЂи®≠еЃЪгБЩгВЛ
- дЉіе•ПгБ™гБЧгБІгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБЃйЯ≥гБ†гБСгВТжµБгБЧгБ™гБМгВЙж≠МгБЖ
- жЛНгБ®иЗ™еИЖгБЃж≠МгБЃгВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гБМеРИгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛйМ≤йЯ≥гБЧгБ¶зҐЇи™НгБЩгВЛ
гБУгВМгВТи°МгБЖгБ®гАБиµ∞гВКгВДйБЕгВМгБЃгВѓгВїгБМгБѓгБ£гБНгВКеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂгАБи£ПжЛНпЉИ2жЛНзЫЃгБ®4жЛНзЫЃпЉЙгБЂжЙЛжЛНе≠РгВТеЕ•гВМгБ™гБМгВЙж≠МгБЖгБ®гАБгВИгВКеЃЙеЃЪгБЧгБЯгГ™гВЇгГ†жДЯгБМиЇЂгБЂгБ§гБНгБЊгБЩгАВ
5. жѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞гБІиА≥гВТйНЫгБИгВЛ
жЬАеЊМгБЂгБКгБЩгБЩгВБгБЧгБЯгБДгБЃгБМжѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞гБІгБЩгАВ
гБУгВМгБѓгАМзРЖжГ≥гБЃж≠МгАНгБ®гАМиЗ™еИЖгБЃж≠МгАНгВТдЇ§дЇТгБЂиБігБПжЦєж≥ХгБІгБЩгАВ
жЙЛй†ЖгБѓз∞°еНШгБІгБЩгАВ
- гБКжЙЛжЬђгБЂгБЧгБЯгБДж≠МжЙЛгБЃйЯ≥жЇРгВТзФ®жДПгБЩгВЛ
- иЗ™еИЖгБЃж≠МгВТеРМгБШдЉіе•ПгГїеРМгБШгВ≠гГЉгБІйМ≤йЯ≥гБЩгВЛ
- гБЭгВМгБЮгВМгВТдЇ§дЇТгБЂиБігБНгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃйБХгБДгВТжОҐгБЩ
зЙєгБЂжДПи≠ШгБЩгБєгБНгБѓжђ°гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЩгАВ
- ж≠МгБДеЗЇгБЧгБЃйЯ≥з®ЛгБ®гВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞
- гГХгГђгГЉгВЇгБЃдЄ≠гБІгБЃеЉЈеЉ±гБЃдїШгБСжЦє
- и™Юе∞ЊгБЃеЗ¶зРЖпЉИдЉЄгБ∞гБЩгАБеИЗгВЛгАБгГУгГЦгГ©гГЉгГИпЉЙ
жѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞гБѓгАБиЗ™еИЖгБІгБѓж∞ЧгБ•гБЛгБ™гБДгГЛгГ•гВҐгГ≥гВєгБЃгВЇгГђгВТзЩЇи¶ЛгБІгБНгВЛйЭЮеЄЄгБЂжЬЙеКєгБ™жЦєж≥ХгБІгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгГЧгГ≠гБЃж≠МжЙЛгБЃгАМйЦУгБЃеПЦгВКжЦєгАНгВДгАМеСЉеРЄгБЃдљНзљЃгАНгВТзЬЯдЉЉгБЩгВЛгБ†гБСгБІгВВгАБгГ™гВЇгГ†жДЯгБМе§ІгБНгБПжФєеЦДгБЧгБЊгБЩгАВ
гГБгВІгГГгВѓжЦєж≥ХгВТзµДгБњеРИгВПгБЫгВЛгБУгБ®гБМйЗНи¶Б
гБУгБУгБЊгБІ5гБ§гБЃжЦєж≥ХгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБжЬАгВВеКєжЮЬзЪДгБ™гБЃгБѓи§ЗжХ∞гБЃжЦєж≥ХгВТзµДгБњеРИгВПгБЫгВЛгБУгБ®гАВ
дЊЛгБИгБ∞гАБйМ≤йЯ≥пЉЛгГФгГГгГБгВҐгГЧгГ™гБІйЯ≥з®ЛгВТгГБгВІгГГгВѓгБЧгАБйМ≤зФїгБІеІњеЛҐгВВ祯и™НгБЩгВЛгАВ
гБВгВЛгБДгБѓгАБжѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞гБ®гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гВТдљµзФ®гБЧгБ¶гГ™гВЇгГ†гВТйНЫгБИгВЛгАБгБ™гБ©гБІгБЩгАВ
гБУгБЖгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАМжДЯи¶ЪгАНгАМи¶Ци¶ЪгАНгАМиБіи¶ЪгАНгБЃгБЩгБєгБ¶гБЛгВЙиЗ™еИЖгБЃж≠МгВТеИЖжЮРгБІгБНгАБжФєеЦДгВєгГФгГЉгГЙгБМж†ЉжЃµгБЂдЄКгБМгВКгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБLiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІгБѓгАБзФЯеЊТжІШеРМе£ЂгБІжЉФе•ПгБЩгВЛж©ЯдЉЪгВТе§ЪгБПи®≠гБСгБ¶гБКгВКгАБзФЯгГРгГ≥гГЙгБІж≠МгБЖж©ЯдЉЪгВТе§ЪгБПи®≠гБСгБ¶гБКгВКгБЊгБЩгАВ
гГЬгВ§гГИгГђгБЃеКєжЮЬгВТзЩЇжПЃгБЩгВЛгВ≥гГДгБѓдЇЇеЙНгБІж≠МгБЖгБУгБ®гАВ
и©≥зі∞гБѓдЄЛи®ШгБЛгВЙгБФ祯и™НгБПгБ†гБХгБДпЉБ
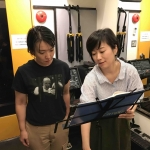
зђђпЉФзЂ†
йЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гВТйНЫгБИгВЛ
гБКгБЩгБЩгВБзД°жЦЩгВҐгГЧгГ™гБ®ж©ЯжЭР
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гВТеЃЙеЃЪгБХгБЫгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБжЧ•гАЕгБЃзЈізњТгБІгАМж≠£зҐЇгБХгАНгВТжДПи≠ШгБІгБНгВЛзТ∞еҐГгБ•гБПгВКгБМйЗНи¶БгБІгБЩгАВ
еєЄгБДгАБдїКгБѓгВєгГЮгГЫгВҐгГЧгГ™гВДжЙЛиїљгБ™ж©ЯжЭРгВТдљњгБИгБ∞гАБиЗ™еЃЕгБІгВВгГЧгГ≠дЄ¶гБњгБЃгГБгВІгГГгВѓгВДгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВ
гБУгБУгБІгБѓгАБLiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІгВВжО®е•®гБЧгБ¶гБДгВЛзД°жЦЩгВҐгГЧгГ™гБ®гАБгБВгВЛгБ®дЊњеИ©гБ™ж©ЯжЭРгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ
1. йЯ≥з®ЛгГБгВІгГГгВѓз≥їгВҐгГЧгГ™
ж≠МгБ£гБЯйЯ≥гВТгГ™гВҐгГЂгВњгВ§гГ†гБІи°®з§ЇгБЧгБ¶гБПгВМгВЛгВҐгГЧгГ™гБѓгАБйЯ≥з®ЛгБЃгВЇгГђгВТеН≥еЇІгБЂзҐЇи™НгБІгБНгВЛеД™гВМгВВгБЃгБІгБЩгАВ
- Vocal Pitch MonitorпЉИAndroid / iOSпЉЙ
иЗ™еИЖгБЃе£∞гВТгГ™гВҐгГЂгВњгВ§гГ†гБІж≥ҐељҐи°®з§ЇгБЧгБ¶гБПгВМгВЛгВҐгГЧгГ™гАВж≠£гБЧгБДйЯ≥гБЃйЂШгБХгБ®гБЃгВЇгГђгВТи¶Ци¶ЪзЪДгБЂжККжП°гБІгБНгБЊгБЩгАВйМ≤йЯ≥ж©ЯиГљгВВгБВгВКгАБеЊМгБІжМѓгВКињФгВКгВВеПѓиГљгАВ - SingScopeпЉИiOSпЉЙ
йЯ≥з®ЛгВТгВ∞гГ©гГХеМЦгБЧгБ¶гБПгВМгВЛгВҐгГЧгГ™гАВйХЈгБДгГХгГђгГЉгВЇгБІгВВгВєгВѓгГ≠гГЉгГЂгБЧгБ™гБМгВЙ祯и™НгБІгБНгАБгБ©гБУгБІйЯ≥гБМгБґгВМгБ¶гБДгВЛгБЛдЄАзЫЃзЮ≠зДґгБІгБЩгАВ - TunableпЉИiOS / AndroidпЉЙ
гГБгГ•гГЉгГКгГЉж©ЯиГљгБ®йМ≤йЯ≥ж©ЯиГљгВТеЕЉгБ≠еВЩгБИгБЯгВҐгГЧгГ™гАВйЯ≥гБЃеЃЙеЃЪеЇ¶гВТжХ∞еА§гБІи©ХдЊ°гБЧгБ¶гБПгВМгВЛгБЯгВБгАБжИРйХЈеЇ¶еРИгБДгВТи®ШйМ≤гБЧгВДгБЩгБДгБІгБЩгАВ
дљњгБДжЦєгБЃгВ≥гГДпЉЪ
гГїжѓОжЧ•еРМгБШжЫ≤гГїеРМгБШгВ≠гГЉгБІжЄђеЃЪгБЩгВЛгБ®гАБеЃЙеЃЪеЇ¶гБЃе§ЙеМЦгБМеИЖгБЛгВКгВДгБЩгБД
гГїгВҐгГЧгГ™гБЃзФїйЭҐгБ∞гБЛгВКи¶ЛгБЪгАБгБЊгБЪиА≥гБІеИ§жЦ≠гБЧгБ¶гБЛгВЙз≠ФгБИеРИгВПгБЫгБЃгВИгБЖгБЂдљњгБЖ
2. гГ™гВЇгГ†гГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞з≥їгВҐгГЧгГ™
гГ™гВЇгГ†жДЯгВТйНЫгБИгВЛгБЂгБѓгАБгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гВДгГ™гВЇгГ†гВ≤гГЉгГ†з≥їгБЃгВҐгГЧгГ™гБМељєзЂЛгБ°гБЊгБЩгАВ
- Metronome BeatsпЉИiOS / AndroidпЉЙ
гГЖгГ≥гГЭпЉИBPMпЉЙгВДжЛНе≠РгВТзі∞гБЛгБПи®≠еЃЪгБІгБНгВЛеЃЪзХ™гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гВҐгГЧгГ™гАВи£ПжЛНгБ†гБСгВТй≥ігВЙгБЩи®≠еЃЪгВВеПѓиГљгАВ - Pro MetronomeпЉИiOS / AndroidпЉЙ
гВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™гБМгВЙйЂШж©ЯиГљгАВгГЖгГ≥гГЭгГБгВІгГ≥гВЄгВДе§ЙжЛНе≠РгБЂгВВеѓЊењЬгБЧгАБзЈізњТжЫ≤гБЃжІЛжИРгБЂеРИгВПгБЫгБЯи®≠еЃЪгБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ - Rhythm Sight Reading TrainerпЉИiOSпЉЙ
гГ™гВЇгГ†и≠ЬгВТи¶ЛгБ™гБМгВЙж≠£гБЧгБПеП©гБПпЉИгБЊгБЯгБѓж≠МгБЖпЉЙзЈізњТгБМгБІгБНгВЛгВҐгГЧгГ™гАВйЫ£жШУеЇ¶и®≠еЃЪгБІеЊРгАЕгБЂгГђгГЩгГЂгВҐгГГгГЧгБІгБНгБЊгБЩгАВ
дљњгБДжЦєгБЃгВ≥гГДпЉЪ
гГїжЬАеИЭгБѓгВЖгБ£гБПгВКгБЃгГЖгГ≥гГЭгБІзЈізњТгБЧгАБе∞СгБЧгБЪгБ§гГЖгГ≥гГЭгВТдЄКгБТгВЛ
гГїи£ПжЛНпЉИ2жЛНзЫЃгБ®4жЛНзЫЃпЉЙгБЂгВҐгВѓгВїгГ≥гГИгВТзљЃгБПгБ®гГОгГ™гБМиЙѓгБПгБ™гВЛ
3. йМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїз≥їгВҐгГЧгГ™
йЂШйЯ≥и≥™гБІйМ≤йЯ≥гБІгБНгВЛгВҐгГЧгГ™гБѓгАБйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБ†гБСгБІгБ™гБПе£∞и≥™гБЃе§ЙеМЦгВВжККжП°гБІгБНгБЊгБЩгАВ
- Voice Record ProпЉИiOS / AndroidпЉЙ
WAV嚥еЉПгБІйЂШйЯ≥и≥™йМ≤йЯ≥гБМеПѓиГљгАВз∞°еНШгБ™зЈ®йЫЖж©ЯиГљдїШгБНгБІгАБдЄНи¶БйГ®еИЖгБЃгВЂгГГгГИгВВгБІгБНгБЊгБЩгАВ - Dolby OnпЉИiOS / AndroidпЉЙ
AIгБМиЗ™еЛХгБІйЯ≥и≥™и£Ьж≠£гВТгБЧгБ¶гБПгВМгВЛйМ≤йЯ≥гВҐгГЧгГ™гАВдЉіе•ПгБ®е£∞гБЃгГРгГ©гГ≥гВєгВВжХігБИгБ¶гБПгВМгБЊгБЩгАВ - FiLMiC ProпЉИiOS / AndroidпЉЙ
еЛХзФїжТЃељ±гБЂзЙєеМЦгБЧгБЯгВҐгГЧгГ™гАВгГЮгВ§гВѓеЕ•еКЫи®≠еЃЪгБМзі∞гБЛгБПгБІгБНгАБи°®жГЕгВДеП£гБЃеЛХгБНгВТ祯и™НгБЩгВЛгБЃгБЂжЬАйБ©гБІгБЩгАВ
4. гБКгБЩгБЩгВБж©ЯжЭР
гВєгГЮгГЫгБ†гБСгБІгВВеНБеИЖгБІгБЩгБМгАБж©ЯжЭРгВТињљеК†гБЩгВЛгБ®зЈізњТгБЃи≥™гБМгБХгВЙгБЂеРСдЄКгБЧгБЊгБЩгАВ
- гВ≥гГ≥гГЗгГ≥гВµгГЉгГЮгВ§гВѓпЉИдЊЛпЉЪAudio-Technica AT2020пЉЙ
е£∞гБЃзі∞гБЛгБДгГЛгГ•гВҐгГ≥гВєгБЊгБІжЛЊгБИгВЛгБЯгВБгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВПгБЪгБЛгБ™гВЇгГђгВВйМ≤йЯ≥гБЂеПНжШ†гБХгВМгБЊгБЩгАВ - гВ™гГЉгГЗгВ£гВ™гВ§гГ≥гВњгГЉгГХгВІгГЉгВєпЉИдЊЛпЉЪFocusrite Scarlett SoloпЉЙ
гГЮгВ§гВѓгБ®PC/гВєгГЮгГЫгВТжО•зґЪгБЧгАБйЂШйЯ≥и≥™гБІйМ≤йЯ≥гБІгБНгВЛж©ЯжЭРгАВгГђгВ§гГЖгГ≥гВЈгГЉпЉИйБЕеїґпЉЙгБМе∞СгБ™гБПгАБдЉіе•ПгБ®еРИгВПгБЫгВДгБЩгБДгБІгБЩгАВ - гГҐгГЛгВњгГЉгГШгГГгГЙгГЫгГ≥пЉИдЊЛпЉЪAudio-Technica ATH-M50xпЉЙ
дЉіе•ПгВДиЗ™еИЖгБЃе£∞гВТж≠£зҐЇгБЂгГҐгГЛгВњгГ™гГ≥гВ∞гБІгБНгАБгГ™гВЇгГ†гВДйЯ≥з®ЛгБЃгВЇгГђгВТеН≥еЇІгБЂжККжП°гБІгБНгБЊгБЩгАВ
5. гВҐгГЧгГ™гБ®ж©ЯжЭРгБЃзµДгБњеРИгВПгБЫдЊЛ
дЊЛгБИгБ∞гБУгВУгБ™зЈізњТгВїгГГгГИгБМиАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВ
- йМ≤йЯ≥пЉЪVoice Record Pro
- йЯ≥з®ЛгГБгВІгГГгВѓпЉЪVocal Pitch Monitor
- гГ™гВЇгГ†зЈізњТпЉЪPro Metronome
- гГҐгГЛгВњгГЉпЉЪгГҐгГЛгВњгГЉгГШгГГгГЙгГЫгГ≥
гБУгБЃзµДгБњеРИгВПгБЫгБ™гВЙгАБйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБЃдЄ°жЦєгВТж≠£зҐЇгБЂжККжП°гБЧгБ™гБМгВЙзЈізњТгБІгБНгБЊгБЩгАВ
гБЊгБ®гВБ
зД°жЦЩгВҐгГЧгГ™гБ®жЬАдљОйЩРгБЃж©ЯжЭРгБ†гБСгБІгВВгАБиЗ™еЃЕгБІгБЃзЈізњТзТ∞еҐГгБѓе§ІгБНгБПеРСдЄКгБЧгБЊгБЩгАВ
зЙєгБЂйЯ≥з®ЛгГБгВІгГГгВѓз≥їгВҐгГЧгГ™гБ®гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБѓгАБгБїгБЉеЕ®гБ¶гБЃгГЬгГЉгВЂгГ™гВєгГИгБЂењЕй†ИгБЃгГДгГЉгГЂгБІгБЩгАВ
жђ°гБЃзђђ5зЂ†гБІгБѓгАБгБУгВМгВЙгБЃгГДгГЉгГЂгВТжіїзФ®гБЧгБЯеЕЈдљУзЪДгБ™йЯ≥з®ЛпЉЖгГ™гВЇгГ†еЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞гВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ

зђђпЉХзЂ†
иЗ™еЃЕзЈізњТгБІдљњгБИгВЛ
йЯ≥з®ЛпЉЖгГ™гВЇгГ†еЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
гБУгБУгБІгБѓгАБеЙНзЂ†гБІзієдїЛгБЧгБЯгВҐгГЧгГ™гВДж©ЯжЭРгВТжіїзФ®гБЧгБ™гБМгВЙгАБиЗ™еЃЕгБІеЃЯиЈµгБІгБНгВЛйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†еЉЈеМЦгГ°гГЛгГ•гГЉгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩгАВ
гБДгБЪгВМгВВ1жЧ•10гАЬ20еИЖгБЛгВЙеІЛгВБгВЙгВМгАБеИЭењГиАЕгБЛгВЙдЄ≠зіЪиАЕгБЊгБІеКєжЮЬгВТеЃЯжДЯгБІгБНгВЛеЖЕеЃєгБІгБЩпЉБ
1. йЯ≥з®ЛеЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
вС† йЯ≥йЪОзЈізњТпЉИгГЙгГђгГЯгГХгВ°гВљгГХгВ°гГЯгГђгГЙпЉЙ
зЫЃзЪДпЉЪеЯЇз§ОзЪДгБ™йЯ≥жДЯгВТеЃЙеЃЪгБХгБЫгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- гГФгВҐгГОгВҐгГЧгГ™гВДгВ≠гГЉгГЬгГЉгГЙгБІгГЙгГђгГЯгГХгВ°гВљгГХгВ°гГЯгГђгГЙгВТеЉЊгБП
- йЯ≥гВТиБігБДгБ¶гБЛгВЙе£∞гБІгБ™гБЮгВЛ
- гВҐгГЧгГ™пЉИVocal Pitch MonitorгБ™гБ©пЉЙгБІйЯ≥гБЃж≠£зҐЇгБХгВТ祯и™Н
гГЭгВ§гГ≥гГИгБѓгАМйЯ≥гВТиБігБДгБЯзЫіеЊМгБЂж≠МгБЖгАНгБУгБ®гАВйЦУгВТз©ЇгБСгВЛгБ®и®ШжЖґгБМжЫЦжШІгБЂгБ™гВКгАБйЯ≥з®ЛгБМдЄНеЃЙеЃЪгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
вС° иЈЭйЫҐгВЄгГ£гГ≥гГЧзЈізњТпЉИгГЙвЖТгВљгАБгГЙвЖТйЂШгБДгГЙгБ™гБ©пЉЙ
зЫЃзЪДпЉЪе§ІгБНгБ™йЯ≥з®ЛзІїеЛХгБІгВВж≠£зҐЇгБЂељУгБ¶гВЙгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБЩгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- гГФгВҐгГОгБІгАМгГЙвЖТгВљгАНгАМгГЙвЖТйЂШгБДгГЙгАНгБ™гБ©5еЇ¶гГї8еЇ¶гБЃйЯ≥гВТй†ЖгБЂеЉЊгБП
- йЯ≥гВТиБігБНгАБгГѓгГ≥гГЖгГ≥гГЭзљЃгБДгБ¶гБЛгВЙж≠£зҐЇгБЂж≠МгБЖ
- йМ≤йЯ≥гБЧгБ¶гАБеИ∞йБФйЯ≥гБМйЂШгБЩгБОгБ™гБДгБЛгГїдљОгБЩгБОгБ™гБДгБЛ祯и™Н
гБУгБЃзЈізњТгБІгАБйЂШйЯ≥гВДдљОйЯ≥гБЂй£ЫгБґгБ®гБНгБЃе§ЦгВМгВТжЄЫгВЙгБЫгБЊгБЩгАВ
вСҐ гВµгВєгГЖгВ£гГ≥пЉИжМБзґЪйЯ≥пЉЙзЈізњТ
зЫЃзЪДпЉЪйЯ≥з®ЛгВТеЃЙеЃЪгБХгБЫгАБжПЇгВМгВТжЄЫгВЙгБЩ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- дїїжДПгБЃйЯ≥пЉИдЊЛпЉЪгГ©пЉЙгВТеЗЇгБЩ
- 4жЛНгАЬ8жЛНгБїгБ©дЉЄгБ∞гБЩ
- гГФгГГгГБгВҐгГЧгГ™гБІйАФдЄ≠гБІйЯ≥гБМдЄЛгБМгБ£гБ¶гБДгБ™гБДгБЛ祯и™Н
жБѓгБЃжФѓгБИгВТдњЭгБ°гАБе£∞гБЃеЃЙеЃЪжДЯгВТй§КгБЖгБУгБ®гБМгГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЩгАВ
2. гГ™гВЇгГ†еЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
вС† гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІж≠МгБЖ
зЫЃзЪДпЉЪжЛНжДЯгВТдљУгБЂжЯУгБњиЊЉгБЊгБЫгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- жЫ≤гБЃгГЖгГ≥гГЭгВТBPMгБІи®≠еЃЪ
- дЉіе•ПгБ™гБЧгБІгАБгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБЂеРИгВПгБЫгБ¶ж≠МгБЖ
- гГ™гВЇгГ†гБМгВЇгГђгБ¶гБДгБ™гБДгБЛйМ≤йЯ≥гБЧгБ¶зҐЇи™Н
и£ПжЛНпЉИ2жЛНзЫЃгГї4жЛНзЫЃпЉЙгВТжДЯгБШгВЛгБ®гАБгГОгГ™гБМиЙѓгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
вС° гГ™гВЇгГ†еИЖиІ£зЈізњТ
зЫЃзЪДпЉЪж≠Ми©ЮгБ®гГ™гВЇгГ†гБЃзЛђзЂЛгВТжДПи≠ШгБЩгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- ж≠Ми©ЮгВТе§ЦгБЧгАБгАМгГ©гАНгВДгАМгВњгАНгБІгГ°гГ≠гГЗгВ£гБ†гБСж≠МгБЖ
- гГ™гВЇгГ†гБМеЃЙеЃЪгБЧгБЯгВЙж≠Ми©ЮгВТжИїгБЩ
ж≠Ми©ЮгВТеК†гБИгВЛгБ®гГ™гВЇгГ†гБМеі©гВМгВДгБЩгБПгБ™гВЛгБЃгБІгАБгБЊгБЪгГ°гГ≠гГЗгВ£гБ†гБСгБІж≠£зҐЇгБХгВТдљЬгВКгБЊгБЩгАВ
вСҐ гВѓгГ©гГГгГЧпЉИжЙЛжЛНе≠РпЉЙзЈізњТ
зЫЃзЪДпЉЪиЇЂдљУгБІгГ™гВЇгГ†гВТеПЦгВЛзњТжЕ£гВТгБ§гБСгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- жЫ≤гБЂеРИгВПгБЫгБ¶жЙЛжЛНе≠РгВТжЙУгБ§пЉИ2жЛНзЫЃгГї4жЛНзЫЃпЉЙ
- гБЭгБЃгБЊгБЊж≠МгБДгБ™гБМгВЙжЙЛжЛНе≠РгВТзґЩзґЪ
гБУгВМгБЂгВИгВКгАБиµ∞гВКгВДйБЕгВМгБМжЄЫгВКгБЊгБЩгАВ
3. йЯ≥з®ЛпЉЖгГ™гВЇгГ†еРМжЩВеЉЈеМЦгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞
вС† гГХгГђгГЉгВЇйМ≤йЯ≥вЖТеН≥еЖНзФЯ
зЫЃзЪДпЉЪзЮђжЩВгБЃгГХгВ£гГЉгГЙгГРгГГгВѓгБІдњЃж≠£еКЫгВТйЂШгВБгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- 1гГХгГђгГЉгВЇж≠МгБ£гБ¶гБЩгБРгБЂеЖНзФЯ
- гВЇгГђгВТжДЯгБШгБЯгВЙеН≥дњЃж≠£гБЧгБ¶еЖНжМСжИ¶
гГ™гВҐгГЂгВњгВ§гГ†гБЃж∞ЧгБ•гБНгБМгАБзњТжЕ£еМЦгВТйШ≤гБОгБЊгБЩгАВ
вС° жѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞пЉИгГЧгГ≠гБ®иЗ™еИЖпЉЙ
зЫЃзЪДпЉЪиА≥гБЃз≤ЊеЇ¶гВТдЄКгБТгВЛ
жЙЛй†ЖпЉЪ
- гБКжЙЛжЬђйЯ≥жЇРгБ®иЗ™еИЖгБЃж≠МгВТдЇ§дЇТгБЂиБігБП
- гВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гВДйЯ≥з®ЛгБЃеЈЃгВТжДПи≠ШгБЩгВЛ
е∞ПгБХгБ™гГЛгГ•гВҐгГ≥гВєгБЃйБХгБДгБЂж∞ЧгБ•гБСгВЛиА≥гБМиВ≤гБ°гБЊгБЩгАВ
4. зЈізњТгГ°гГЛгГ•гГЉдЊЛпЉИ1жЧ•20еИЖпЉЙ
- йЯ≥йЪОзЈізњТпЉИгГЙгГђгГЯгГХгВ°гВљгГХгВ°гГЯгГђгГЙпЉЙвА¶5еИЖ
- иЈЭйЫҐгВЄгГ£гГ≥гГЧзЈізњТвА¶3еИЖ
- гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІж≠МгБЖвА¶5еИЖ
- жѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞вА¶5еИЖ
- и®ШйМ≤пЉИзЈізњТгГ°гГҐпЉЙвА¶2еИЖ
зЯ≠жЩВйЦУгБІгВВжѓОжЧ•зґЪгБСгВМгБ∞гАБиА≥гБ®е£∞гБЃз≤ЊеЇ¶гБМе∞СгБЧгБЪгБ§дЄКгБМгВКгБЊгБЩгАВ
жђ°гБЃзђђ6зЂ†гБІгБѓгАБгБУгБЃжИРйХЈгВТ嶮гБТгВЛгВДгБ£гБ¶гБѓгБДгБСгБ™гБДNGзЈізњТж≥ХгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ
жЭ±дЇђгБЃLiveArtгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гБѓгБУгБ°гВЙ
зђђ6зЂ†
еИЭењГиАЕгБМгВДгВКгБМгБ°гБ™
NGзЈізњТж≥Х
иЗ™еЃЕзЈізњТгБІйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гВТдЄКйБФгБХгБЫгБЯгБДгБ®жАЭгБ£гБ¶гВВгАБйЦУйБХгБ£гБЯзЈізњТгВТзґЪгБСгВЛгБ®йАЖеКєжЮЬгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВ…гАВ
гБУгБУгБІгБѓеИЭењГиАЕгБМйЩ•гВКгВДгБЩгБДNGзЈізњТж≥ХгБ®гАБгБЭгБЃжФєеЦДз≠ЦгВТиІ£и™ђгБЧгБЊгБЩгАВ
1. йЯ≥з®ЛгВТж∞ЧгБЂгБЫгБЪеЛҐгБДгБІж≠МгБЖ
NGгБЃеЖЕеЃєпЉЪдЉіе•ПгБЂеРИгВПгБЫгБЪгАБеЛҐгБДгБ†гБСгБІж≠МгБЖ
еХПй°МзВєпЉЪиА≥гБІзҐЇи™НгБЫгБЪгБЂзЈізњТгБЩгВЛгБ®гАБйЦУйБХгБ£гБЯйЯ≥з®ЛгБМзњТжЕ£еМЦгБХгВМгБЊгБЩгАВзЙєгБЂйЂШйЯ≥гВДдљОйЯ≥гБІгБѓйЯ≥з®ЛгБМгБґгВМгВДгБЩгБПгАБдњЃж≠£гБЂжЩВйЦУгБМгБЛгБЛгВКгБЊгБЩгАВ
жФєеЦДз≠ЦпЉЪ
- йМ≤йЯ≥гБЧгБ¶йЯ≥з®ЛгВТ祯и™НгБЩгВЛ
- гГФгГГгГБгВҐгГЧгГ™гБІгВЇгГђгВТи¶Ци¶ЪеМЦгБЩгВЛ
- йЯ≥йЪОзЈізњТгБІеЯЇз§ОгВТеЫЇгВБгБ¶гБЛгВЙжЫ≤гБЂжМСжИ¶гБЩгВЛ
2. йХЈжЩВйЦУдЄАж∞ЧгБЂзЈізњТгБЩгВЛ
NGгБЃеЖЕеЃєпЉЪйЫЖдЄ≠еКЫгБМзґЪгБЛгБ™гБДгБЊгБЊ30еИЖдї•дЄКйА£зґЪгБІж≠МгБЖ
еХПй°МзВєпЉЪзЦ≤еКігБЂгВИгБ£гБ¶е£∞гБМдЄНеЃЙеЃЪгБЂгБ™гВКгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМеі©гВМгВДгБЩгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВзЙєгБЂйЂШйЯ≥гБѓзЦ≤гВМгБІгВЈгГ£гГЉгГЧгВДгГХгГ©гГГгГИгБЂгБ™гВКгВДгБЩгБДгБІгБЩгАВ
жФєеЦДз≠ЦпЉЪ
- 10гАЬ20еИЖгБФгБ®гБЂдЉСжЖ©гВТжМЯгВА
- зЯ≠жЩВйЦУгБІи≥™гБЃйЂШгБДзЈізњТгВТзє∞гВКињФгБЩ
- и®ШйМ≤гВТеПЦгВКгАБжФєеЦДзВєгВТжђ°еЫЮгБЂжіїгБЛгБЩ
3. дЉіе•ПгБ™гБЧгБІж≠МгБДзґЪгБСгВЛ
NGгБЃеЖЕеЃєпЉЪдЉіе•ПгБ™гБЧгБІиЗ™еЈ±жµБгБ†гБСгБІж≠МгБЖ
еХПй°МзВєпЉЪгГ™гВЇгГ†жДЯгВДжЛНжДЯгБМйНЫгБИгВЙгВМгБЪгАБжЫ≤еЕ®дљУгБЃжµБгВМгВТгБ§гБЛгВБгБ™гБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВгГЖгГ≥гГЭгБМиµ∞гБ£гБЯгВКйБЕгВМгБЯгВКгБЩгВЛеОЯеЫ†гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жФєеЦДз≠ЦпЉЪ
- ењЕгБЪдЉіе•ПгВДгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гВТдљњгБЖ
- и£ПжЛНгВДеЉЈжЛНгВТжДПи≠ШгБЧгБ¶ж≠МгБЖ
- йМ≤йЯ≥гБЧгБ¶гАБдЉіе•ПгБ®гВЇгГђгБ¶гБДгБ™гБДгБЛ祯и™НгБЩгВЛ
4. йМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїгВТгБЫгБЪиЗ™еЈ±еИ§жЦ≠гБ†гБСгБІзЈізњТ
NGгБЃеЖЕеЃєпЉЪгАМиЗ™еИЖгБЃиА≥гБ†гБСгАНгБІзЈізњТгБЩгВЛ
еХПй°МзВєпЉЪиЗ™еИЖгБЃиА≥гБѓй™®дЉЭе∞ОгБІйЯ≥гБМдљОгВБгБЂиБЮгБУгБИгВЛгБЯгВБгАБж≠£зҐЇгБ™йЯ≥з®ЛеИ§жЦ≠гБМгБІгБНгБЊгБЫгВУгАВгГ™гВЇгГ†гВВиЗ™еЈ±жДЯи¶ЪгБ†гБСгБІгБѓгВЇгГђгБЂж∞ЧгБ•гБНгБЂгБПгБДгБІгБЩгАВ
жФєеЦДз≠ЦпЉЪ
- гВєгГЮгГЫгБІйМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїгБЩгВЛ
- йМ≤йЯ≥гВТиБігБНгАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгВТгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛ
- еЛХзФїгБІеІњеЛҐгВДеП£гБЃйЦЛгБНжЦєгВВ祯и™НгБЩгВЛ
5. еРМгБШзЈізњТж≥ХгВТзє∞гВКињФгБЩгБ†гБС
NGгБЃеЖЕеЃєпЉЪжѓОжЧ•еРМгБШжЫ≤гВДеРМгБШгГХгГђгГЉгВЇгБ†гБСгВТзє∞гВКињФгБЩ
еХПй°МзВєпЉЪеБПгБ£гБЯзЈізњТгБЂгБ™гВКгАБйЯ≥еЯЯгВДгГ™гВЇгГ†гГСгВњгГЉгГ≥гБЃеєЕгБМеЇГгБМгВКгБЊгБЫгВУгАВзµРжЮЬзЪДгБЂењЬзФ®еКЫгБМиВ≤гБ°гБЂгБПгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жФєеЦДз≠ЦпЉЪ
- йЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гГїи°®зПЊеКЫгВТжДПи≠ШгБЧгБ¶зЈізњТеЖЕеЃєгВТе§ЙгБИгВЛ
- гВєгВ±гГЉгГЂзЈізњТгВДиЈЭйЫҐгВЄгГ£гГ≥гГЧзЈізњТгАБи£ПжЛНзЈізњТгБ™гБ©гВВзµДгБњеРИгВПгБЫгВЛ
- гБКжЙЛжЬђйЯ≥жЇРгБЃгГХгГђгГЉгВЇгВТзЬЯдЉЉгБЧгБ¶жѓФиЉГгГ™гВєгГЛгГ≥гВ∞гБЩгВЛ
гБЊгБ®гВБ
NGзЈізњТгБЃеЕ±йАЪзВєгБѓиЗ™еЈ±жµБгБ†гБСгБІеЃМзµРгБЧгБ¶гБЧгБЊгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ
йМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїгГїгВҐгГЧгГ™гГїгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБ™гБ©гВТжіїзФ®гБЧгАБеЄЄгБЂеЃҐи¶≥зЪДгБЂиЗ™еИЖгВТгГБгВІгГГгВѓгБЩгВЛгБУгБ®гБМгАБйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гБЃеЃЙеЃЪгБЂгБѓдЄНеПѓжђ†гБІгБЩгАВ
жђ°зЂ†гБІгБѓгАБгБУгВМгБЊгБІгБЃеЖЕеЃєгВТиЄПгБЊгБИгБЯиЗ™еЃЕзЈізњТгВТжЬАе§ІеМЦгБЩгВЛзњТжЕ£гБ•гБПгВКгВТиІ£и™ђгБЧгБЊгБЩпЉБ
зђђпЉЧзЂ†
иЗ™еЃЕгГЬгВ§гГИгГђзЈізњТгВТ
жЬАе§ІеМЦгБЩгВЛзњТжЕ£гБ•гБПгВК
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гВТжФєеЦДгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБж≠£гБЧгБДзЈізњТж≥ХгБ†гБСгБІгБ™гБПгАБзњТжЕ£еМЦгБЩгВЛдїХзµДгБњгВВйЗНи¶БгБІгБЩгАВ
иЗ™еЃЕгГЬгВ§гГИгГђзЈізњТгБЃеКєжЮЬгВТжЬАе§ІеМЦгБЩгВЛгБЯгВБгБЃеЕЈдљУзЪДгБ™зњТжЕ£гБ•гБПгВКгБЃжЦєж≥ХгВТзієдїЛгБЧгБЊгБЩпЉБ
1. жѓОжЧ•ж±ЇгБЊгБ£гБЯжЩВйЦУгБЂзЈізњТгБЩгВЛ
зњТжЕ£еМЦгБЃеЯЇжЬђгБѓгАБж≠МгБЃзЈізњТжЩВйЦУгВТжѓОжЧ•еЫЇеЃЪгБЩгВЛгБУгБ®гБІгБЩгАВ
дЊЛгБИгБ∞гАБжЬЭиµЈгБНгБ¶гБЛгВЙ15еИЖгАБжШЉдЉСгБњгБЂ10еИЖгАБеѓЭгВЛеЙНгБЂ15еИЖгБ™гБ©гАБиЗ™еИЖгБЃзФЯжіїгГ™гВЇгГ†гБЂзµДгБњиЊЉгБњгБЊгБЩгАВ
жЩВйЦУгВТеЫЇеЃЪгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБзЈізњТгБМгАМзЊ©еЛЩжДЯгАНгБІгБѓгБ™гБПгАМељУгБЯгВКеЙНгБЃгГЂгГЉгГЖгВ£гГ≥гАНгБЂгБ™гВКгАБзґЩзґЪгБМеЃєжШУгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
2. зЈізњТеЙНгБЂзЫЃж®ЩгВТи®≠еЃЪгБЩгВЛ
гБЯгБ†йЧЗйЫ≤гБЂж≠МгБЖгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБдїКжЧ•гБЃзЈізњТгБЃгВігГЉгГЂгВТж±ЇгВБгБЊгБЩгАВ
дЊЛпЉЪ
- йЯ≥йЪОзЈізњТгБІйЂШйЯ≥гБЃеЃЙеЃЪгВТ祯и™НгБЩгВЛ
- гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІжЫ≤гБЃгГ™гВЇгГ†гВТеі©гБХгБЪж≠МгБЖ
- йМ≤йЯ≥гБЧгБЯгГХгГђгГЉгВЇгБЃгВЇгГђгВТдњЃж≠£гБЩгВЛ
зЫЃж®ЩгВТжШО祯гБЂгБЩгВЛгБ®гАБзЈізњТгБЃи≥™гБМж†ЉжЃµгБЂдЄКгБМгВКгБЊгБЩгАВ
3. и®ШйМ≤гВТгБ§гБСгВЛ
зЈізњТгБЃеЖЕеЃєгВДж∞ЧгБ•гБНгВТгГОгГЉгГИгВДгВєгГЮгГЫгВҐгГЧгГ™гБЂи®ШйМ≤гБЧгБЊгБЩгАВ
и®ШйМ≤гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИпЉЪ
- гБ©гБЃгГХгГђгГЉгВЇгБМйЯ≥з®ЛгВЇгГђгВДгГ™гВЇгГ†гВЇгГђгВТиµЈгБУгБЧгВДгБЩгБДгБЛ
- еСЉеРЄгВДеІњеЛҐгБЃжФєеЦДзВє
- зЈізњТеЊМгБЃжДЯи¶ЪпЉИзЦ≤еКіеЇ¶гАБе£∞гБЃеЃЙеЃЪжДЯгБ™гБ©пЉЙ
еЊМгБІжМѓгВКињФгВЛгБУгБ®гБІгАБиЗ™еИЖгБЃжИРйХЈгВДи™≤й°МгВТеЃҐи¶≥зЪДгБЂзҐЇи™НгБІгБНгБЊгБЩгАВ
4. е∞ПгБХгБ™жИРеКЯдљУй®УгВТйЗНгБ≠гВЛ
йЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБМеЃЙеЃЪгБЩгВЛгБ®гАБйБФжИРжДЯгБМзФЯгБЊгВМгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃе∞ПгБХгБ™жИРеКЯдљУй®УгВТз©НгБњйЗНгБ≠гВЛгБУгБ®гБІгАБзЈізњТгБЃгГҐгГБгГЩгГЉгВЈгГІгГ≥гВТзґ≠жМБгБІгБНгБЊгБЩгАВ
йМ≤йЯ≥гБЧгБЯиЗ™еИЖгБЃе£∞гБМ1йА±йЦУеЙНгВИгВКгВВеЃЙеЃЪгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®жДЯгБШгВЙгВМгБЯгВЙгАБгБЭгБЃжЧ•гБ†гБСгБѓиЗ™еИЖгВТи§ТгВБгВЛзњТжЕ£гВТгБ§гБСгВЛгБЃгВВгБКгБЩгБЩгВБгБІгБЩгАВ
5. еЃҐи¶≥зЪДгГБгВІгГГгВѓгВТзњТжЕ£еМЦгБЩгВЛ
йМ≤йЯ≥гГїйМ≤зФїгГїгВҐгГЧгГ™гВТжіїзФ®гБЧгБЯгГБгВІгГГгВѓгБѓгАБжѓОеЫЮгБЃзЈізњТгБІи°МгБДгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
гБУгВМгБЂгВИгВКгАМиЗ™еЈ±жµБгБІж∞ЧгБ•гБЛгБ™гБДгВЇгГђгАНгВТжЄЫгВЙгБЧгАБеКєзОЗзЪДгБЂжФєеЦДгБІгБНгБЊгБЩгАВ
жЕ£гВМгБ¶гБНгБЯгВЙгАБгГБгВІгГГгВѓжЩВйЦУгВТжЬАеИЭгБЂ5еИЖгБ†гБСеПЦгВЛгБ™гБ©гАБзЯ≠жЩВйЦУгБІгВВзњТжЕ£еМЦгБЩгВЛгБ®еКєжЮЬзЪДгБІгБЩгАВ
6. зЈізњТзТ∞еҐГгВТжХігБИгВЛ
е£∞гБМж≠£зҐЇгБЂиБігБУгБИгВЛзТ∞еҐГгВТдљЬгВЛгБУгБ®гВВзњТжЕ£еМЦгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЩгАВ
- еПНйЯњгБМе∞СгБ™гБДйГ®е±ЛгБІзЈізњТгБЩгВЛ
- гГҐгГЛгВњгГЉгГШгГГгГЙгГЫгГ≥гВДгВєгГФгГЉгВЂгГЉгВТдљњзФ®гБЩгВЛ
- дЉіе•ПйЯ≥йЗПгВТйБ©еИЗгБЂи®≠еЃЪгБЩгВЛ
зТ∞еҐГгБМжХігБЖгБ®гАБйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃгВЇгГђгБЂгБЩгБРж∞ЧгБ•гБСгАБжФєеЦДгВВгВєгГ†гГЉгВЇгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
7. зД°зРЖгБЫгБЪзґЩзґЪгБЩгВЛ
жИРйХЈгБЂгБѓжЩВйЦУгБМгБЛгБЛгВКгБЊгБЩгАВ1еЫЮгБЃзЈізњТгБІеЃМзТІгВТзЫЃжМЗгБХгБЪгАБе∞СгБЧгБЪгБ§жФєеЦДгБЩгВЛжДПи≠ШгВТжМБгБ§гБУгБ®гБМе§ІеИЗгБІгБЩгАВ
жѓОжЧ•е∞СгБЧгБЪгБ§гБІгВВзґЪгБСгВЛгБУгБ®гБІгАБеНКеєіеЊМгАБ1еєіеЊМгБЂгБѓзҐЇеЃЯгБЂе§ЙеМЦгБМзПЊгВМгБЊгБЩгАВ
8. гГЧгГ≠гБЂзЫЄиЂЗгБЩгВЛ
иЗ™еЃЕзЈізњТгБѓе§ІеИЗгБІгБЩгБМгАБзЛђе≠¶гБ†гБСгБІгБѓж∞ЧгБ•гБСгБ™гБДгВѓгВїгВДжФєеЦДзВєгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ
LiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІгБѓгАБеИЭењГиАЕгБІгВВеЃЙењГгБЧгБ¶йАЪгБИгВЛгГЬгГЉгВЂгГЂгВ≥гГЉгВєгВТзФ®жДПгБЧгБ¶гБКгВКгАБгГЧгГ≠иђЫеЄЂгБМгБВгБ™гБЯгБЃйЯ≥з®ЛгГїгГ™гВЇгГ†гВТзЪД祯гБЂгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБПгВМгБЊгБЩгАВ
жЭ±дЇђгБЃLiveArtгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гБѓгБУгБ°гВЙ
иЗ™еЃЕгБІгБЃзЈізњТгВТжЬАе§ІйЩРгБЂжіїгБЛгБЧгАБгГЧгГ≠гБЃжМЗе∞ОгБІгБХгВЙгБЂдЄКйБФгВТеК†йАЯгБХгБЫгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
ж≠£гБЧгБДзњТжЕ£гБ®еЃҐи¶≥зЪДгГБгВІгГГгВѓгБІгАБгБВгБ™гБЯгБЃж≠Ме£∞гБѓзҐЇеЃЯгБЂеЃЙеЃЪгБЧгАБзРЖжГ≥гБЃйЯ≥з®ЛгБ®гГ™гВЇгГ†гБМиЇЂгБЂгБ§гБНгБЊгБЩпЉБ

зђђпЉШзЂ†
гВИгБПгБВгВЛи≥™еХПгБ®гГЧгГ≠гБЃеЫЮз≠Ф
- Q1: иЗ™еЃЕгБІгБЃйМ≤йЯ≥гБ†гБСгБІжЬђељУгБЂдЄКйБФгБЧгБЊгБЩгБЛпЉЯ
A1: йМ≤йЯ≥гБІиЗ™еИЖгБЃе£∞гВТеЃҐи¶≥и¶ЦгБЩгВЛгБУгБ®гБѓйЭЮеЄЄгБЂжЬЙеКєгБІгБЩгБМгАБж≠£гБЧгБДжЦєж≥ХгВТзњТжЕ£еМЦгБЩгВЛгБУгБ®гБМйЗНи¶БгБІгБЩгАВйА±1еЫЮгБѓгГЧгГ≠гБЂгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гВВгВЙгБЖгБ®еКєжЮЬгБМжЧ©гБЊгВКгБЊгБЩгАВ - Q2: йЂШйЯ≥гБМеЃЙеЃЪгБЧгБЊгБЫгВУгАВгБ©гБЖгБЩгВМгБ∞гВИгБДгБІгБЩгБЛпЉЯ
A2: иЕєеЉПеСЉеРЄгБ®жФѓгБИгВТжДПи≠ШгБЧгАБзД°зРЖгБЂе£∞гВТжКЉгБЧеЗЇгБХгБ™гБДгБУгБ®гБМгГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЩгАВиЈЭйЫҐгВЄгГ£гГ≥гГЧзЈізњТгБІеЊРгАЕгБЂжЕ£гВМгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ - Q3: гГ™гВЇгГ†гБМиµ∞гВЛгГїйБЕгВМгВЛгБЃгБІгБЩгБМпЉЯ
A3: гГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБЂеРИгВПгБЫгБ¶зЯ≠гБДгГХгГђгГЉгВЇгБЛгВЙзЈізњТгБЩгВЛгБ®еЃЙеЃЪгБЧгБЊгБЩгАВжЙЛжЛНе≠РгБІиЇЂдљУжДЯи¶ЪгВТгБ§гБСгВЛгБЃгВВгБКгБЩгБЩгВБпЉБ -
гБЊгБ®гВБ
йЯ≥з®ЛгБ®гГ™гВЇгГ†гБѓгАМиА≥гАНгБ®гАМзњТжЕ£гАНгБІе§ЙгВПгВЛйЯ≥з®ЛгВДгГ™гВЇгГ†гБЃжФєеЦДгБЂгБѓгАБж≠£гБЧгБДзЈізњТж≥ХпЉЛзњТжЕ£еМЦгБМдЄНеПѓжђ†гБІгБЩгАВйМ≤йЯ≥гГїгВҐгГЧгГ™гГїгГ°гГИгГ≠гГОгГЉгГ†гБІеЃҐи¶≥зЪДгБЂзҐЇи™НгБЧгАБе∞СгБЧгБЪгБ§жФєеЦДгВТз©НгБњйЗНгБ≠гВЛгБУгБ®гБІгАБи™∞гБІгВВеЃЙеЃЪгБЧгБЯж≠Ме£∞гВТжЙЛгБЂеЕ•гВМгВЙгВМгБЊгБЩгАВ
LiveArtйЯ≥ж•љжХЩеЃ§гБІгБѓгАБеИЭењГиАЕгБІгВВеЃЙењГгБЧгБ¶йАЪгБИгВЛгГЬгГЉгВЂгГЂгВ≥гГЉгВєгВТзФ®жДПгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гГЧгГ≠иђЫеЄЂгБЂгВИгВЛгГБгВІгГГгВѓгБІгАБиЗ™еЃЕзЈізњТгБЃжИРжЮЬгВТгБХгВЙгБЂеК†йАЯгБХгБЫгБЊгБЧгВЗгБЖпЉБжЭ±дЇђгБЃLiveArtгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гБѓгБУгБ°гВЙ
гБУгБЃи®ШдЇЛгВТеЯЈз≠ЖгБЧгБЯ
жЭ±дЇђгБЃLiveArtгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§гБЂгБ§гБДгБ¶- ж≠МгБ®гБЃеЗЇдЉЪгБДгБІгАБеЕЕеЃЯгБЃжЧ•гАЕгВТ
- йЯ≥ж•љгБЃе••жЈ±гБХгВТжДЯгБШгБ¶гАБи±КгБЛгБ™жДЯжАІгВТ
- гГЬгГЉгВЂгГЂгБЃж•љгБЧгБХгБ®жКАи°УгВТгАБгБЭгБЧгБ¶зЯ•и≠ШгБ®зµМй®УгВТ
е†іжЙАгВТйБЄгБєгВЛгГЬгГЉгВЂгГЂжХЩеЃ§
гГЬгВ§гГИгГђгБВгВКпЉБжЭ±дЇђгААжЦ∞еЃњгААйЂШзФ∞й¶ђе†ігАА汆иҐЛгААе§Іе°ЪгААеЈ£йі®
йІТиЊЉгААдЄКйЗОгААзІЛиСЙеОЯгААж±ЯеП§зФ∞гААзЈій¶ђгГ©гВ§гГ≥гБЛгВЙгБЃгБКеХПгБДеРИгВПгБЫгВВе§Іж≠УињОгБІгБЩпЉБ